高学歴の人に青春コンプレックスが多い理由を考えると、彼らの人生が学業中心に設計されている点がまず挙げられる。
難関校や有名大学を目指すには、子供の頃から膨大な時間を勉強に費やす必要がある。たとえば、小学生で塾に通い、中学生で部活を犠牲にして模試に備え、高校生では毎晩遅くまで受験勉強に励む。このような生活では、青春時代に典型的な友人との遊びや恋愛、趣味に没頭する時間が大幅に削られる。学校が終わればすぐに塾へ行き、休日も参考書を開く日々が続けば、同級生が恋人と手を繋いで歩いたり、仲間と旅行に行ったりする姿を横目に「自分には関係ない」と割り切るしかない。そうした経験の欠如が、後に「青春を逃した」というコンプレックスに変わる。
さらに、高学歴の人にはコミュニケーション能力が低いケースが散見されることも、このコンプレックスを助長する。勉強に多くの時間を割く生活では、他者と気軽に交流する機会が減り、社交性が育ちにくいのだ。たとえば、学校での雑談やグループでの遊びに参加するよりも、一人で問題集を解くことを選ぶ人が多い。また、受験勉強は競争原理に基づいているため、他人を仲間ではなく敵と見なす癖がつくこともある。
この結果、感情を共有したり、空気を読んで会話を弾ませたりする能力が不足しがちになる。特に恋愛では、相手との距離を縮めるための自然な振る舞いやユーモアが求められるが、高学歴の人は「論理的には正しいはずなのに、なぜかうまくいかない」と感じることが多い。
これが、青春時代に恋愛や友情を深められなかった原因となり、コンプレックスを強める。親の教育方針も、高学歴者の青春コンプレックスに影を落としている。
多くの場合、高学歴を重視する家庭では、「勉強が人生の全て」「恋愛は時間の無駄」「モテることは不良の特徴」といった価値観が子供に押しつけられる。たとえば、成績優秀な子が異性に興味を示すと、「そんなことに気を取られるな」とたしなめられることが多い。このような環境では、モテることや恋愛を楽しむことが「軽薄」「不真面目」と結びつき、青春らしい行動を自ら遠ざけるようになる。
親が「不良っぽい子は将来性がない」と強調すれば、社交的で異性に人気のある同級生を避け、内向的な生活に逃げ込む傾向が強まる。その結果、青春時代に恋愛や友情の経験が乏しくなり、「自分は普通の楽しさを味わえなかった」という思いが残る。
このコンプレックスは、大人になってからも影響を及ぼす。たとえば、職場で同僚が学生時代の思い出を語るのを聞くと、高学歴の人は「自分にはそんなエピソードがない」と疎外感を抱く。
また、学歴やキャリアでは成功を収めていても、「普通の青春」がなかったことへの未練が心に残る。SNSで他人の楽しそうな過去を見ると、比較による劣等感がさらに増す。高学歴という達成感と引き換えに失った青春の時間が、彼らにとって埋められない空白となるのだ。

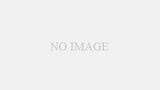
コメント